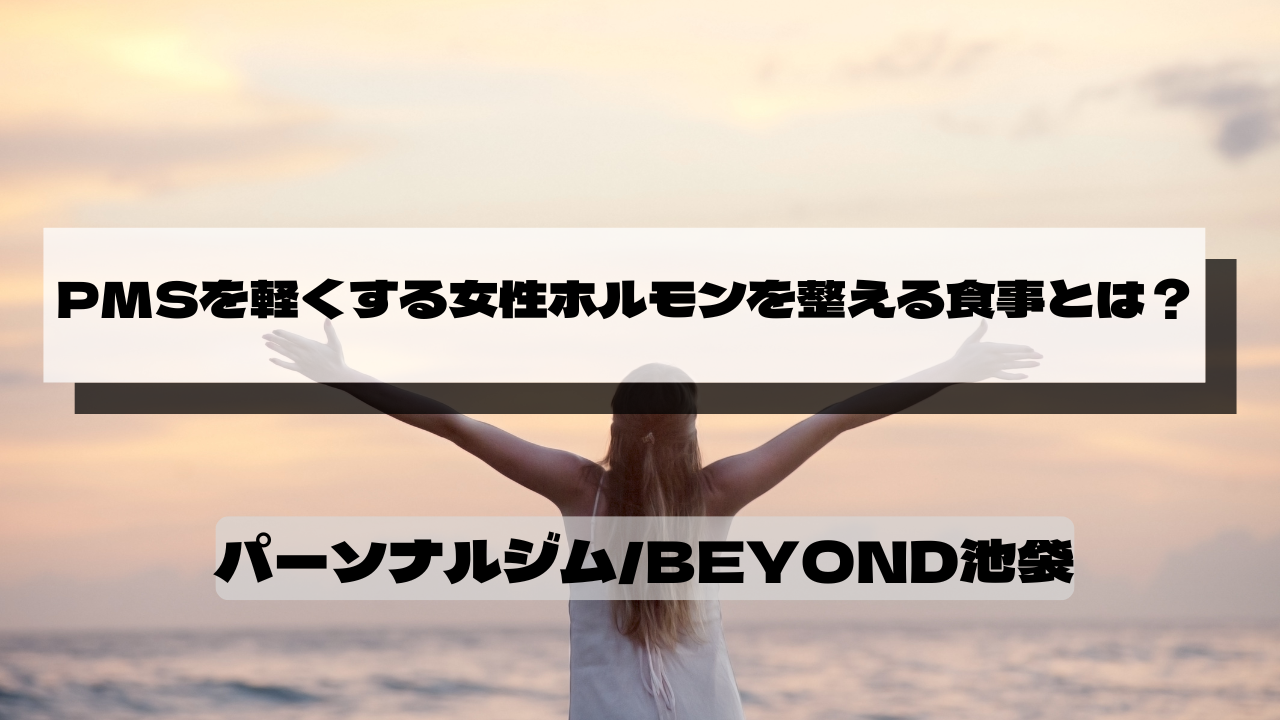月経前になると決まって現れるイライラ、憂鬱感、腹痛、頭痛、むくみ。
これらの症状に毎月悩まされている女性は決して少なくありません。
日本産科婦人科学会の調査によると、生殖年齢女性の約80%が何らかのPMS症状を経験しており、そのうち約20%は日常生活に支障をきたすほど重篤な症状を抱えています。
PMS(月経前症候群)は、月経開始の3-10日前から現れる身体的・精神的症状の総称です。
現代女性のライフスタイルの変化により、ストレス増加、食生活の乱れ、運動不足などが複合的に作用し、PMS症状は年々深刻化しています。
しかし、適切な食事療法により女性ホルモンのバランスを整えることで、これらの症状は大幅に改善できることが数多くの研究により実証されています。
重要なのは、女性ホルモンの働きと食事の関係を理解し、科学的根拠に基づいた効果的な栄養戦略を実践することです。
この記事をご覧いただいている方へ。
この記事をご覧いただいている皆さまは、健康面に気を使い、食生活や運動習慣の見直し、フィットネスジムに通われている。もしくは、入会等をご検討されている健康意識の高い方々ではないでしょうか?
実際に、厚生労働省が、健康づくりのための身体活動基準・指針を作成し、生活習慣病予防のための運動を推進しています。
また、日本政策金融公庫が発表した消費者動向調査(令和3年7月)では、運動面や食に関する志向で、“健康志向”の方が多く年々と増加しています。
より皆様が、健康的で充実した人生を歩めるよう、誠意を込めて記事を執筆いたしましたので、どうか最後までご覧ください。
<その他資料>
※スポーツ庁の資料(新型コロナウイルス感染症の流行による国民のスポーツへの参画状況や意識の変化、健康状態等に関する調査研究(令和2年度))では、コロナ終息後のパーソナルトレーニングジムの利用者数は急増中。
※経済産業省の『特定サービス産業動態統計速報』の結果でも、フィットネスジム並びに、パーソナルジム利用者は数多くいらっしゃいます。
【PR】BEYOND

BEYONDは全国150店舗以上を展開する、BEST GYM AWARD受賞のパーソナルジム。美ボディコンテストでの入賞者や資格をもつ、プロのパーソナルトレーナーのみが揃っております。
過度な食事制限やトレーニングなく、ライフスタイルに合わせて無理なく継続できます。
コースは大きく以下3つにわかれているため、目的に合ったトレーニングを選択可能です。
| 料金(税込) ※最小プランの場合 | 内容 | おすすめ | |
| ライフプランニングコース | 月々18,500~ ※323,664円 | パーソナルトレーニング 食事管理 サプリメント | 目標がある方向け |
| 回数券コース | 月々4,700円~ ※102,300円 | パーソナルトレーニング ストレッチ | 継続したい方向け |
※当社指定の信販会社を利用した際の分割料金となります。・10回券96,800円の場合:分割回数:24回/支払い期間:24ヶ月/手数料率:年利7.96%/支払い総額:115,850円
特に回数券コースの月々4,800円~は、業界内でも最安値級で良心的です。
BEYONDが気になる方は、まず無料体験トレーニングを活用してみてください。
\今なら入会金50,000円が無料/
PMSと女性ホルモンの関係:科学的メカニズムを解明

PMSの根本的な原因を理解するためには、まず女性ホルモンの周期的変動とその身体への影響を把握することが重要です。
こちらの把握をしていなかった…という女性の方は実際多くいらっしゃいます。
痩せやすい時期やそうではない時期を把握できるので、ダイエットをされる方にとっても有益な情報となるでしょう。
月経周期における女性ホルモンの変動
女性の月経周期は、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の複雑な相互作用により調節されています。
月経周期の前半(卵胞期)にはエストロゲンが優位となり、気分の安定、エネルギーレベルの向上、認知機能の改善などの効果をもたらします。
排卵後の後半(黄体期)には、プロゲステロンが急激に上昇します。
プロゲステロンは妊娠の維持に重要な役割を果たしますが、同時に水分貯留、食欲増進、気分の不安定化などの副作用も引き起こします。
月経前にプロゲステロンが急激に低下することで、神経伝達物質のバランスが乱れ、PMS症状が発現します。
これが痩せづらいタイミングでもあります。気分も落ちやすいですから、『しょうがないのか。。』を受容して、なるべく体重が増えない様にアプローチを続ける必要があります。
| 月経周期 | 主要ホルモン | 身体への影響 | 主な症状 |
|---|---|---|---|
| 月経期(1-5日) | エストロゲン・プロゲステロン低値 | 子宮内膜剥離、炎症反応 | 月経痛、疲労感 |
| 卵胞期(6-13日) | エストロゲン上昇 | 気分安定、エネルギー向上 | 体調良好、活動的 |
| 排卵期(14日前後) | エストロゲンピーク | 最良のコンディション | 症状最小、高パフォーマンス |
| 黄体期(15-28日) | プロゲステロン優位 | 水分貯留、食欲増進 | PMS症状発現 |
神経伝達物質への影響
女性ホルモンの変動は、脳内の神経伝達物質に直接的な影響を与えます。セロトニンは「幸せホルモン」として知られ、気分の安定、睡眠の質、食欲調節に重要な役割を果たします。
エストロゲンの低下により脳内セロトニン濃度が減少し、抑うつ気分、不安、過食などのPMS症状が引き起こされます。
GABA(ガンマアミノ酪酸)は脳の興奮を抑制する神経伝達物質で、リラクゼーションと不安軽減に重要です。プロゲステロンの代謝産物であるアロプレグナノロンは、GABA受容体を活性化しますが、月経前のプロゲステロン急降下により、この鎮静効果が失われ、イライラや不安が増大します。
ドーパミンは意欲と快感に関わる神経伝達物質です。
エストロゲンはドーパミンの合成と放出を促進するため、エストロゲンの低下により意欲減退、集中力低下、無気力感などの症状が現れます。
炎症反応と代謝への影響
女性ホルモンの変動は、全身の炎症反応と代謝にも大きな影響を与えます。
プロゲステロンの影響により、月経前にはプロスタグランジンE2などの炎症性物質の産生が増加し、頭痛、関節痛、乳房の張りなどの身体症状が引き起こされます。
また、プロゲステロンはインスリン感受性を低下させ、血糖値の不安定化を引き起こします。
これにより甘いものへの渇望が増加し、血糖値の急激な上昇と下降により気分の変動が悪化します。
さらに、アルドステロンの作用により水分とナトリウムの貯留が促進され、むくみと体重増加が生じます。
科学的根拠に基づく食事療法の効果

栄養学と婦人科学の研究により、適切な食事療法がPMS症状の軽減と女性ホルモンバランスの改善に大きな効果をもたらすことが証明されています。
American Journal of Clinical Nutritionに掲載された大規模研究では、適切な栄養介入により PMS症状が平均40-60%改善することが報告されています。
食事療法の効果は多面的です。
まず、特定の栄養素が神経伝達物質の合成と機能を直接的に改善します。
トリプトファンはセロトニンの前駆体であり、適切な摂取により気分の安定化が期待できます。
マグネシウムはGABA受容体の機能を改善し、不安とイライラを軽減します。
また、抗炎症作用のある栄養素により、PMS期の炎症反応を抑制できます。
オメガ3脂肪酸は強力な抗炎症作用を持ち、プロスタグランジンの産生を調節することで、頭痛や関節痛などの身体症状を軽減します。
血糖値の安定化も重要な効果です。複合炭水化物と食物繊維の適切な摂取により、血糖値の急激な変動を防ぎ、気分の安定化と甘いものへの渇望を抑制できます。
さらに、利尿作用のある栄養素により、水分貯留とむくみを改善できます。
PMS改善に効果的な栄養素と食材

PMS症状の軽減と女性ホルモンバランスの改善には、特定の栄養素を戦略的に摂取することが重要です。
以下は、科学的研究により効果が実証された主要な栄養素とその食材源です。
難しい食材ではありませんので、日常的に摂取することを目標にしましょう。
セロトニン合成促進栄養素
トリプトファンは、セロトニンの直接的な前駆体として、気分の安定化に最も重要な栄養素です。トリプトファンが豊富な食材には、七面鳥、鶏肉、魚類、卵、乳製品、大豆製品、ナッツ類、バナナなどがあります。効果的な摂取のためには、炭水化物と組み合わせることで脳内への取り込みが促進されます。
ビタミンB6は、トリプトファンからセロトニンへの変換に必要な補酵素です。不足するとセロトニン合成が阻害され、PMS症状が悪化します。ビタミンB6が豊富な食材には、鶏肉、魚類、バナナ、アボカド、ほうれん草、ひよこ豆、玄米などがあります。1日の推奨摂取量は1.2-1.4mgです。
マグネシウムは、300以上の酵素反応に関与し、神経系の正常な機能に不可欠です。マグネシウム不足はPMS症状の悪化と強く関連しており、補給により症状の大幅な改善が期待できます。マグネシウムが豊富な食材には、ダークチョコレート、ナッツ類、種子類、緑葉野菜、全粒穀物、豆類などがあります。
抗炎症・ホルモン調節栄養素
オメガ3脂肪酸は、強力な抗炎症作用により、PMS期の身体症状を大幅に軽減します。EPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)は、プロスタグランジンの産生を調節し、頭痛、関節痛、乳房の張りなどを改善します。オメガ3が豊富な食材には、サーモン、サバ、イワシ、亜麻仁、チアシード、くるみなどがあります。
ビタミンEは、強力な抗酸化作用と抗炎症作用を持ち、PMS症状の軽減に効果的です。特に乳房の張りと痛みの改善に優れた効果を示します。ビタミンEが豊富な食材には、アーモンド、ひまわりの種、アボカド、ほうれん草、ブロッコリー、植物油などがあります。
亜鉛は、ホルモンの合成と代謝に重要な役割を果たし、女性ホルモンバランスの調節に不可欠です。亜鉛不足はPMS症状の悪化と関連しており、適切な補給により症状の改善が期待できます。亜鉛が豊富な食材には、牡蠣、赤身肉、鶏肉、豆類、ナッツ類、種子類などがあります。
血糖値安定化栄養素
複合炭水化物は、血糖値の安定化により気分の変動を抑制し、甘いものへの渇望を軽減します。精製された単純炭水化物とは異なり、複合炭水化物は緩やかに消化吸収され、持続的なエネルギー供給を提供します。優良な複合炭水化物源には、玄米、全粒小麦、オーツ麦、キヌア、さつまいも、豆類などがあります。
食物繊維は、血糖値の急激な上昇を防ぎ、腸内環境を改善することで全身の炎症を抑制します。また、エストロゲンの代謝と排出を促進し、ホルモンバランスの改善に寄与します。食物繊維が豊富な食材には、野菜類、果物類、全粒穀物、豆類、ナッツ類などがあります。1日25-35gの摂取が推奨されます。
クロムは、インスリンの作用を改善し、血糖値の安定化に重要な役割を果たします。クロム不足は血糖値の不安定化と甘いものへの渇望を引き起こし、PMS症状を悪化させます。クロムが豊富な食材には、ブロッコリー、全粒穀物、赤身肉、卵、ナッツ類などがあります。
月経周期に合わせた食事戦略

女性ホルモンの周期的変動に合わせて食事内容を調整することで、より効果的なPMS対策が可能になります。各期間の生理学的特徴を理解し、適切な栄養戦略を実践することが重要です。
| 月経周期 | 重点栄養素 | 推奨食材 | 避けるべき食品 |
|---|---|---|---|
| 月経期 | 鉄分、ビタミンC、抗炎症成分 | 赤身肉、緑葉野菜、柑橘類、生姜 | カフェイン、アルコール、冷たい食品 |
| 卵胞期 | タンパク質、ビタミンB群、亜鉛 | 魚類、卵、全粒穀物、ナッツ類 | 過度な糖分、加工食品 |
| 排卵期 | 抗酸化物質、オメガ3、食物繊維 | ベリー類、緑黄色野菜、魚類 | 炎症性食品、トランス脂肪酸 |
| 黄体期 | マグネシウム、ビタミンB6、複合炭水化物 | ダークチョコレート、バナナ、玄米 | 塩分、単純糖質、カフェイン |
月経期(1-5日目)の栄養戦略
月経期は、月経血による鉄分の喪失と炎症反応により、特別な栄養ケアが必要です。鉄分の補給は最優先事項であり、ヘム鉄が豊富な赤身肉、レバー、魚類の摂取を増やします。非ヘム鉄の吸収を促進するため、ビタミンCが豊富な柑橘類、ベリー類、緑黄色野菜と組み合わせて摂取します。
炎症反応を抑制するため、抗炎症作用のある食材を積極的に取り入れます。生姜、ターメリック、緑茶、ダークチョコレートなどは、プロスタグランジンの産生を抑制し、月経痛の軽減に効果的です。また、温かい食べ物と飲み物により血行を促進し、子宮の収縮を和らげます。
この期間は消化機能が低下しやすいため、消化に良い食材を選択します。スープ、煮込み料理、蒸し野菜などの調理法により、栄養素の吸収を最適化します。カフェインとアルコールは血管収縮作用により月経痛を悪化させる可能性があるため、摂取を控えます。
卵胞期(6-13日目)の栄養戦略
卵胞期は、エストロゲンの上昇により代謝が活発になり、エネルギー需要が増加します。高品質なタンパク質の摂取により、ホルモンの合成と細胞の修復を支援します。魚類、鶏肉、卵、大豆製品などの完全タンパク質を1日体重1kgあたり1.2-1.6g摂取します。
ビタミンB群は、エネルギー代謝とホルモン合成に重要な役割を果たします。特にビタミンB6、B12、葉酸の摂取を重視し、全粒穀物、緑葉野菜、レバー、魚類を積極的に摂取します。この期間は食欲が安定しているため、バランスの取れた食事計画を立てやすい時期です。
運動能力が向上する時期でもあるため、運動前後の栄養補給を適切に行います。運動前には複合炭水化物でエネルギーを確保し、運動後にはタンパク質で筋肉の回復を促進します。水分補給も重要で、1日2-2.5リットルの水分摂取を心がけます。
黄体期(15-28日目)のPMS対策栄養戦略
黄体期は、PMS症状が現れる最も重要な時期であり、戦略的な栄養介入が必要です。
マグネシウムの摂取を大幅に増やし、1日400-600mgを目標とします。ダークチョコレート(カカオ70%以上)、アーモンド、ほうれん草、アボカドなどを積極的に摂取し、神経系の安定化を図ります。
複合炭水化物の摂取により、セロトニンの合成を促進し、気分の安定化を図ります。
玄米、オーツ麦、キヌア、さつまいもなどの低GI食品を選択し、血糖値の急激な変動を防ぎます。甘いものへの渇望が強くなる時期ですが、精製糖質は避け、自然な甘味料や果物で代替します。
水分貯留対策として、カリウムが豊富な食材を摂取し、ナトリウムの摂取を制限します。
バナナ、アボカド、ほうれん草、トマトなどのカリウム豊富な食材により、体内の水分バランスを調節します。塩分の多い加工食品、外食は避け、自然な調味料を使用した手作り料理を心がけます。
PMS改善のための実践的食事プラン

理論的な知識を実際の食生活に活かすため、具体的な食事プランとレシピを提案します。
これらのプランは、忙しい現代女性でも実践しやすいよう、簡単で栄養価の高い内容に設計されています。
人間の習慣化は『14日〜66日』と言われています。
人によって差はありますが、実践を繰り返し、改善を続けて習慣化させましょう。
黄体期のPMS対策1日食事プラン
朝食(7:00-8:00)では、血糖値の安定化とセロトニン合成の促進を重視します。オーツ麦にバナナ、アーモンド、チアシードをトッピングしたボウルに、無糖ヨーグルトを加えます。飲み物は、マグネシウムが豊富なココア(無糖)または緑茶を選択します。この組み合わせにより、トリプトファン、マグネシウム、複合炭水化物を効率的に摂取できます。
昼食(12:00-13:00)では、タンパク質と抗炎症成分を重視します。サーモンのグリル(オメガ3豊富)に、キヌアサラダ(緑葉野菜、アボカド、ナッツ入り)を組み合わせます。ドレッシングは、オリーブオイルとレモン汁のシンプルなものを使用し、抗炎症効果を最大化します。
間食(15:00-16:00)では、血糖値の維持と甘いものへの渇望対策を行います。ダークチョコレート(カカオ70%以上)1-2片と、アーモンド10粒程度の組み合わせにより、マグネシウムと健康的な脂質を補給します。または、バナナとアーモンドバターの組み合わせも効果的です。
夕食(18:00-19:00)では、リラクゼーションと翌日への準備を重視します。鶏胸肉のハーブ焼きに、ローストした根菜類(さつまいも、人参、ブロッコリー)を添えます。炭水化物は玄米または全粒パンを適量摂取し、夜間のセロトニン合成を促進します。
PMS症状別の特別レシピ
イライラ・不安対策レシピ:マグネシウムリッチスムージーでは、ほうれん草1カップ、バナナ1本、アーモンドバター大さじ1、チアシード小さじ1、無糖ココアパウダー小さじ1、アーモンドミルク1カップを組み合わせます。このスムージーは、マグネシウム、トリプトファン、オメガ3を豊富に含み、神経系の鎮静化に効果的です。
むくみ対策レシピ:カリウムたっぷりサラダでは、アボカド1個、トマト1個、きゅうり1本、ほうれん草2カップ、レモン汁大さじ2、オリーブオイル大さじ1を組み合わせます。カリウムが豊富で利尿作用があり、水分貯留の改善に効果的です。塩分は使用せず、ハーブで風味を付けます。
疲労・だるさ対策レシピ:鉄分補給スープでは、赤身牛肉100g、ほうれん草2カップ、トマト2個、玉ねぎ1個、にんにく2片、生姜1片を使用します。鉄分、ビタミンC、抗炎症成分を組み合わせ、エネルギーレベルの向上と炎症の抑制を図ります。
避けるべき食品とその理由

PMS症状の改善には、有益な食品の摂取と同様に、症状を悪化させる食品の回避も重要です。科学的研究により、特定の食品がPMS症状を増悪させることが明らかになっています。
精製糖質と単純炭水化物は、血糖値の急激な上昇と下降を引き起こし、気分の変動を悪化させます。白砂糖、白米、白パン、菓子類、清涼飲料水などは、インスリンの急激な分泌を促し、その後の血糖値低下により、イライラ、不安、疲労感が増大します。また、炎症反応を促進し、PMS期の身体症状も悪化させます。
過剰な塩分は、水分貯留を促進し、むくみと体重増加を悪化させます。加工食品、インスタント食品、外食には大量の塩分が含まれており、1日の推奨摂取量(6g未満)を大幅に超過しやすくなります。塩分の過剰摂取は、血圧上昇と腎臓への負担も増加させ、全身の循環機能に悪影響を与えます。
カフェインは、適量であれば問題ありませんが、過剰摂取は不安とイライラを増大させます。特にPMS期には、カフェインに対する感受性が高まるため、通常量でも症状が悪化する可能性があります。1日のカフェイン摂取量は200mg以下(コーヒー2杯程度)に制限し、午後以降の摂取は避けます。
アルコールは、一時的にはリラックス効果をもたらしますが、長期的には睡眠の質を低下させ、ホルモンバランスを乱します。また、肝臓でのエストロゲン代謝を阻害し、ホルモンの蓄積を引き起こします。PMS期には、アルコールの摂取を最小限に抑えるか、完全に避けることが推奨されます。
サプリメントの効果的な活用法

バランスの取れた食事が基本ですが、現代の食生活では十分な栄養素を摂取することが困難な場合があります。科学的根拠に基づいたサプリメントの適切な活用により、PMS症状の改善を加速できます。
マグネシウムサプリメントは、PMS改善に最も効果的なサプリメントの一つです。クエン酸マグネシウムまたはグリシン酸マグネシウムの形態で、1日200-400mgの摂取が推奨されます。就寝前の摂取により、リラクゼーション効果と睡眠の質向上も期待できます。
ビタミンB6サプリメントは、セロトニン合成の促進により、気分症状の改善に効果的です。1日50-100mgの摂取により、PMS症状の有意な改善が報告されています。ただし、長期間の高用量摂取(200mg以上)は神経障害のリスクがあるため、適切な用量を守ることが重要です。
オメガ3脂肪酸サプリメントは、抗炎症作用により身体症状の改善に効果的です。EPA 1000mg、DHA 500mg程度の組み合わせで、1日1-2回摂取します。魚アレルギーがある場合は、藻類由来のオメガ3サプリメントを選択します。
プロバイオティクスは、腸内環境の改善により、全身の炎症抑制とホルモンバランスの調節に寄与します。特に、ラクトバチルス・ロイテリやビフィドバクテリウム・ロンガムなどの菌株が、PMS症状の改善に効果的であることが報告されています。
ライフスタイルとの統合戦略

食事療法の効果を最大化するためには、運動、睡眠、ストレス管理などの他のライフスタイル要因との統合が重要です。包括的なアプローチにより、より大きな改善効果が期待できます。
運動との組み合わせでは、有酸素運動と筋力トレーニングの両方を取り入れます。運動により血行が促進され、栄養素の組織への供給が改善されます。また、運動後の栄養補給タイミングを最適化することで、筋肉の回復とホルモンバランスの改善を促進できます。
睡眠の質の改善は、ホルモンバランスの調節に不可欠です。就寝前の食事内容を調整し、トリプトファンとマグネシウムが豊富な軽食を摂取することで、睡眠の質を向上させます。カフェインとアルコールは睡眠を阻害するため、夕方以降の摂取は避けます。
ストレス管理では、瞑想、ヨガ、深呼吸などのリラクゼーション技法と組み合わせます。ストレス軽減により、コルチゾールレベルが低下し、女性ホルモンバランスが改善されます。また、ストレス食いを防ぐことで、食事計画の継続も容易になります。
効果測定と継続のための戦略

食事療法の効果を客観的に評価し、継続的な改善を図るためには、適切な測定方法と継続戦略が必要です。
症状日記の記録により、食事内容とPMS症状の関連性を把握します。毎日の食事内容、症状の程度(1-10段階)、気分の変化を記録し、パターンを分析します。特に、特定の食品摂取後の症状変化に注目し、個人的な食品感受性を特定します。
体重と体組成の変化を月経周期と関連付けて記録します。健康的な食事療法により、PMS期の体重変動が減少し、全体的な体組成が改善されます。また、むくみの程度を客観的に評価するため、足首や手首の周囲径を定期的に測定します。
血液検査による栄養状態の評価を3-6ヶ月ごとに実施します。鉄分、ビタミンB12、葉酸、ビタミンD、マグネシウムなどの血中濃度を測定し、栄養療法の効果を客観的に評価します。不足している栄養素があれば、食事内容やサプリメントの調整を行います。
継続のための戦略として、食事の準備を簡素化し、週末にまとめて調理する「ミールプレップ」を活用します。また、家族や友人との情報共有により、社会的サポートを活用します。完璧を求めすぎず、80%の実践で十分な効果が得られることを理解し、柔軟性を保つことが長期継続の鍵となります。
専門的サポートが必要な場合の判断基準

食事療法は多くのPMS症状に効果的ですが、重篤な症状や根本的な疾患がある場合は専門的な治療が必要です。以下の症状がある場合は、婦人科や内科への相談を検討してください。
重度のPMS症状として、日常生活や仕事に重大な支障をきたす場合は、PMDD(月経前不快気分障害)の可能性があります。自殺念慮、重度の抑うつ、パニック発作などの精神症状がある場合は、精神科での専門的治療が必要です。
月経不順や無月経がある場合は、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)や甲状腺疾患などの内分泌疾患の可能性があります。異常な体重変化や、食事療法にもかかわらず症状が改善しない場合は、根本的な代謝異常や栄養吸収障害の可能性があるため、医学的評価が必要です。
まとめ:健やかな女性ホルモンバランスへの確実な道筋

PMSは現代女性にとって深刻な問題ですが、科学的根拠に基づいた食事療法により確実に改善できます。重要なのは継続性と個人の症状に応じたカスタマイズです。
まずは月経周期の記録と症状日記から始めて、徐々に食事内容を調整していくことをお勧めします。
完璧を求めすぎず、小さな変化を積み重ねることで、大きな改善効果が期待できます。
健やかな女性ホルモンバランスは、女性の健康と生活の質を大幅に向上させる基盤となります。
今日から、たった一つの食品を変えることから始めてみませんか。
小さな一歩が、あなたのホルモンバランスと人生を変える大きな変化の始まりとなるでしょう。
継続こそが成功の鍵であり、無理をせず自分のペースで取り組むことが最も重要です。